
こんにちは。ねぼのすけです。今回は、ねぼのすけベイビーが6月に産まれるということで、”ねぼのすけ 育休を取る”という題材で国が育休における改正が行われていること、育休を取った経緯や懸念点など育休を取るにあたって経験したことを記事に書いていこうと思います。
育児休業法の改正
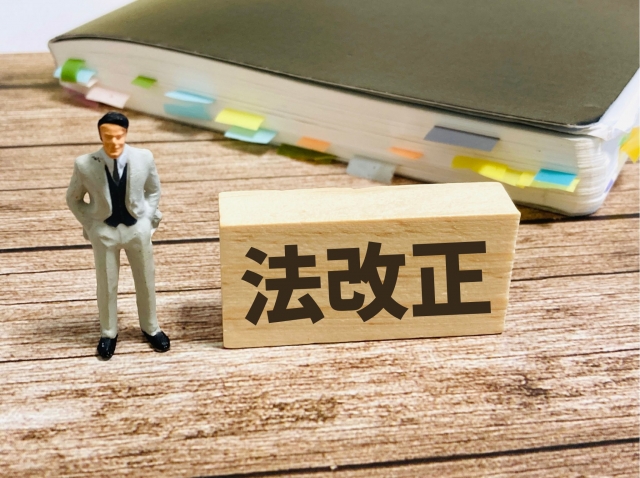
令和4年4月より、育児・介護休業法の改正がありました。内容としては、ざっくり大きく三つあります。それは、
- 雇用環境整備/育児休業取得状況の公表義務化
- 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
- 育休制度自体の見直し
です。
雇用環境整備/育児休業取得状況の公表義務化
この改正は簡単にいうと、育休と取りやすくするよう会社側が考慮しようという話です。
内容としては、会社側が育休中に関する相談窓口を設置したり、育休取得に関する情報を周知し、育休を促進する必要があるということです。
また、会社は、社員から妊娠(配偶者も含む)の報告があった際、育休を実際の有無にかかわらず、育休するかどうかの意向確認を必ずしなければならないのです。つまり会社・上司は育休制度について知らなければならないし、それを社員に伝える必要があるということです。
さらに、従業員が1000人超えの企業は育児休業等の取得状況を年1回公表することも義務化されました。
つまり、どの会社が育児に対して前向きなのかが数字で出ますので今後は就活の際や世間の評価にも繋がってきますので、会社側としても率先して育休取得を取ってもらいたいと思うわけです。
育休制度自体の見直し
今までの育児休業制度は1つしかなく、1回しか取得出来なかったのですが、改正後は分割して2回取得できようになったのと、1歳以降の延長の開始日のタイミングが自由になり制度として柔軟化しました。
さらに産後パパ育休という休業制度が追加され、育児休業とは別に新たな休業が設置されました。育休を1回だけ1年未満で取得する予定の方は特に変わりない制度となります。
しかし、複数回に分けて育休を取得したい方には、産後パパ育休と通常の育児休業を併用して柔軟に取得できるようになりました。
詳細は、以下の厚生労働省のHPで詳細を確認することが出来ます。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
育休を取った経緯
私は当初育休を取ることは全く考えていませんでしたし、育休の制度についてもほとんど知りませんでした。そんな私が育休を取ることになった経緯を書いていこうと思います。
子供や妻との時間を大切にしたい

今、世の中は数年前と比べると上記に記載したように国も会社も育児休職を取得しやすい環境になったと思います。育休を一番に取りたいと思ったのは、子どもの成長を見たいからです。
子供の成長は一瞬だと言いますし、産まれた直後の赤ちゃんと貴重な時間を一緒に過ごしたいという思いがありましたし、妻の負担を少しでも減らしたいので育休を取れるのであれば取りたいと思っていました。
育休を取る前の不安

とはいえ、実際に自分が休職をするとなると周りに迷惑をかけないか、周りの態度が冷たくならないかなど、制度として環境整備されていても自分の身近にいる人の視線は気になるものです。
また、仕事に遅れと取ったらどうしよう、仕事が回ってこなくなるかもといった事も思いました。ただそれは結局、”今の現状に変化”があるのを自分自身で怖がっていただけで、実際は上司も快く承諾してくれましたし、周りは「そうなんだ~頑張ってね!」くらいの感じでした。
なので、ねぼのすけは育休を2か月間取ることにしました。
育休を取ると起こる現実問題
いざ育休を取るぞ!!と決意をしたわけですが、育児休業を取得するにあたって現実問題というか懸念することがあります。それは”お金”です。なぜ育休を2か月にしたかの理由もこの”お金”と”子育ての時間”の兼ね合いを考えた結果だからです。育休中は会社からの給料は発生しません。その代わり育児休業給付金という公的制度です。この育児休業給付金の支払額の目安は
- 育休開始から6か月まで:休業開始時賃金日額×支給日数×67%
- 育休開始から6か月超えたら:休業開始時賃金日額×支給日数×50%
です。
この休業開始時賃金日額は直近6か月の賃金総額÷180で算出します。賃金総額は残業代や交通費なども含まれます。
また、社会保険料が免除になり、大変ありがたい制度です。
しかし、やはり通常働いている時より収入が落ちるのは確実なので、家計にもそこまでダメージが少なく、子どもの成長も見ることができる2か月という期間にしました。
今後育休を考えている方は、この”お金”と”子供と過ごす時間”の両立ができる期間を夫婦の中でできちんと話し合って決めていければと思います。将来的に、政府は給付金を賃金の全額にするという話も出ているみたいなので、より良い方向に制度が変わっていくことも期待です。
いかかでしたでしょうか。今回は育休を取ることにした経緯やその制度についての記事でした。次回は、子供が産まれる前の準備や事前に買っておいた物について記事を書きたいと思います。
最後まで御覧いただきありがとうございました。
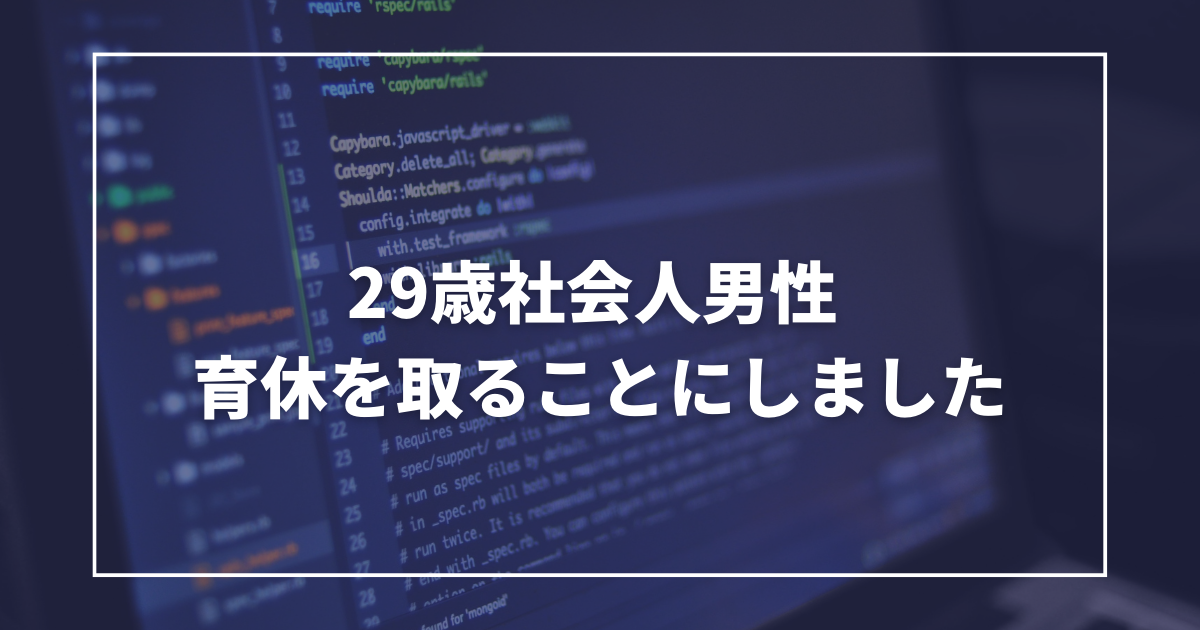
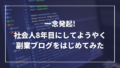
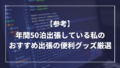
コメント